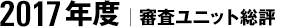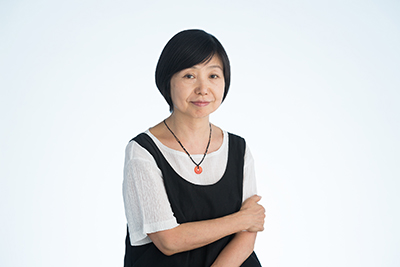本年度のグッドデザイン賞の審査も、領域別に応募対象をグループ分けした「審査ユニット」ごとに審査が行われました。各ユニットでの審査を通じて見られた傾向や特徴、領域ごとのデザインの状況や課題をまとめました。
本ユニットの審査を終えて、まず感じたことは少人数の組織によるデザインが多いな、ということである。数人(あるいは一人!)で商品を企画し、製造してしまう、ということが本格的に可能になってきたのだな、と感じた。
また、開発者が本当に欲しいものを突き詰めていった結果、これまでニッチだと言われてきた、どうせ売れやしないだろうと見向きもされなかった市場に対しても社会の注目が集まっていく。そんな印象を受けた。
なぜこんな現象が起きているのか?
残念ながらいまのところ明確な論拠はもっていない。
しかし、理由の一つとして、つくりたい人とつくる人のダイレクトなコミュニケーションが加速している現状を挙げてもいいだろう。
「こういうものが作りたい」と思う。インターネットで作りかたを調べているうちに作ってくれそうな工場が見つかる。まだ細かいところまでは決まってないけれど、とにかく足を運んで相談を持ちかけてみる。話を進めているうちに興にのってきて、いつのまにか、できてしまう。
そういう風景が、もはや特別なものではなくなっているのではないだろうか。
小さな組織、あるいは個人の強い動機にもとづく行動が、確実にものづくりを動かしているのだ。
よく言われることではあるが、小さな組織は決定までのプロセスがじつに短い。さっさと作ってさっさと改善する。自分たちが開発者であり、責任者だから遠慮なくやり直せる。
つくっていて、いらないな、と思うものは最初から問題外。
そうやって、本当にほしいと思って作られたものだからこそ、多くの共感を得られるのだろう。それが何よりの、小さな組織の強みである。
つくりたいと思う人がつくることができるようになった。
そうやってつくられたものこそが共感を得て、社会に出るようになった。
そんな画が見えてくる審査であった。

-
デザイナー/クリエイティブディレクター
- ユニット02:生活プロダクト(趣味・健康用品)
A1-08 衛生・美容・健康用品/家庭用医療器具、A1-11 スポーツ・アウトドア/レジャー・ホビー・園芸用品
ユニット2はおもに趣味・健康用品のカテゴリーの審査ユニットであり、限定された場面での使用がメインとなる。応募対象についても、アウトドア用品から爪切りなどの日用品、楽器などまで幅広く、どれもデザイナーやメーカーの感じた問題解決に対する想いの強さを感じる商品ばかりだった。そういった商品を前に私たちユニット2の審査員が審査の評価基準として考慮したのは、「使う場所、使う時間、使う人に対して適した(違和感のない)ものになっているか」であった。それは、いくら技術的に新しくとも、形が魅力的でも、その点を踏まえないと暮らしの中に違和感を生んでしまうと考えているからである。モノは必ず使う空間、場所があり、使う時間、そして人との交わりがある。そういったモノを取り巻く環境に馴染むよう丁寧に形に思いを落とし込んでいる商品を良いデザインと評価した。
このユニットの審査対象の傾向として挙げられる点は、既存製品の後継機を継続して改良を重ねた商品が多く見られたということである。一見、代わり映えのしない商品に感じるものもあるかもしれないが、先に述べた私たちの評価基準を踏まえ、環境に落とし込むプロセスを丁寧に踏んでいる商品を評価した。
一方、残念だったのは、売場にて競合製品との差異を出すために加えられた、過度に感じてしまうデザインが少なからず見受けられたことである。もちろん審査員である我々もデザイナーであり、クライアントとの開発プロセスでそういった議論になることも経験している。しかし、丁寧にデザインされた商品はたとえ地味と感じてしまうようなものでも、評価に値する商品として違いはしっかりと表れる。その追加した装飾によって今回の審査を通らなかったものもあり、受賞とそうでなかった商品の差異は、最後までぶれずにものづくりをやりきったかどうかによるものだと感じている。過度な装飾を用いて売場にデザインの良し悪しを委ねるのでなく、簡単ではないが、作り手が本当に欲しいものを生み出し、良いデザインとはこういうものだという訴求活動まで信念を持ってやり遂げてほしいと感じている。
このユニットは、生活雑貨、日用品が対象のユニットで、生まれて間もない新生児のための日用品から、亡くなられた後に必要になる墓石や仏壇まで、対象の種類は多岐にわたる。また、家事の負担を無くす為の生活用品や、障害を持った方が使い易いものなど、日常生活を便利にする道具が多いのも特徴的である。
日常を便利にする生活用品は、消費者の意見をもとに改良を加えていくため、多くの製品は使い勝手が良く、機能性に長けた製品が多い。だがその機能を求める日本の傾向は少し偏ってもいる。欧米の製品も日本と同じく消費者の要望に応えながらブラッシュアップを重ね、機能的にも優れたものが多いが、同時に形状の美しさを併せ持つものも多い。対して、これまでの日本の生活用品は機能に優れているものが多いが、便利グッズの領域を超えない製品が少なくなかった。これはデザインの重要性を認識し、企業のブランディングが確立している欧米企業と、ものづくりに特化してきた日本の企業の考え方の違いが大きく影響している。
昨年の応募製品は、日常を豊かにするために様々な機能を追加したものや、伝統的工芸品に新しいテクノロジーを加える足し算の製品が多かったが、今年はより機能を追求しながらも、余計なものをそぎ落とす引き算の製品が多く見られた。そして、消費者に伝える手段として多くの企業がブランディングに力を入れてきたのは今年の大きな変化であった。大きな投資や改良ではなく、視点を少し変えるだけで、より現代的な製品に生まれ変わらせる手法は、地方の小さなものづくりの企業が生き残る有効な手段となることを、強く感じた審査であった。
仕組みのデザインや、社会的なテーマ性の強いものの割合が増えてきている近年のグッドデザイン賞であるが、ユニット4では白物家電や家庭用品という典型的な工業製品が対象であり、近年の傾向に加えて、まずはプロダクトデザインの基本的な評価基準を持って審査が行われた。
このユニットでは、確実に進化していく家電製品などに対し、ガラスや陶磁器のように、デザインの対象としては王道的にも関わらず、技術が成熟しているが故に進化しにくい製品もある。その中にあって、例え大きな進化がなくても、私たちの生活を変える可能性を秘めた「美しい」ものをどのように評価し、審査委員で共有するかということを改めて考える機会となった。ものの魅力や有用性は、単純な評価基準だけでは計れない。
ハリオの「ショットグラス / 5oz グラス」(17G040224)、大堀相馬焼松永窯の「クロテラス」(17G040214)、ベスト100に選ばれた東洋佐々木ガラスの「フィーノ」(17G040207)など、今回選出されたものは、世にある今までのものとは大きく変わらぬ様に見えながら、時代や生活様式に合わせて地味ながらも確実に新しいアイデンティティを形作っている。一方で受賞に至らなかった対象では、機能的で外観にまとまりのあるもの、地域社会への貢献が見られるもの、ユニバーサルな機能を考慮したものなどであっても、果たして本当に良いデザイン(=グッドデザイン)かと問われると、やはり何かが足りない、ということも少なくなかった。美しいという感覚が得られないのである。
美しいということは、人や自然と同じく、一つはそのものの存在のしかたに対して言うのではないか。選出された対象は、外観のみならずこういった美しさを持っていたと思う。
賞全体で見ても、仕組みや背景が重視されることはグッドデザイン賞のアイデンティティであり、審査基準として重要なのは間違いないが、それら対象のデザインが本当に美しいのか、ということに着目するのは、加えて非常に重要である。象徴的な応募が少なからず見られたユニット4の審査は、そういったデザインや賞の本質について考えさせられるものであった。
多種多様な商品やサービスが一堂に会するグッドデザイン賞の審査において、拠り所の一つとなるのが審査委員向けに配布される「審査委員チュートリアルブック」である。(ウェブサイトでも公開されているので応募者にも一読をお薦めしたい。)そこには審査に対する視点や基本的な考え方が記載されているが、その中の一つに「審査のウエイト」という項目がある。応募対象を「十分な実績を積んだ改善型」と「全く新しい新規型」に分け、改善型については「デザインの適切性」を、新規型については「将来の可能性」を重視して審査を行うよう求めるものである。今回の審査を通してこの点についての議論が多くなされたと感じており改めて振り返っておきたい。
この2つの審査基準は、実績あるプロダクトの正常進化も、新しいジャンルを切り開くイノベーションも、両方の価値を評価するための考え方であるが、では「改善型」は既存のターゲットユーザーに受け入れられる正常進化のみを目指し、新しいチャレンジをしなくてもよいかといえばそうではないだろう。テクノロジーが分野の垣根をなくし、グローバル化も進む中で、同じ分野の競合商品だけでなく、思わぬ異分野のイノベーションに顧客を奪われることも今後ますます起きてくるだろう。顧客の声に耳を傾け着実な進化を続けながらも、今までにない新たな価値を生み出す革新への意識も同時に求められる。
一方で、クラウドファンディング型の商品開発プロセスを大企業も取り入れるといった試みも生まれる中、斬新な発想や最新のテクノロジーを活かして新しいジャンルを切り開こうとするプロダクトが多く応募されているのも近年の傾向である。このような「新規型」は、プレゼンテーションやプロトタイプによって「将来の可能性」を感じさせることはもちろん重要であるが、一方で「改善型」に求められるような細部にわたるユーザビリティの配慮やプロダクトデザインとしての完成度に目をつぶってよいというわけではない。特に情報機器分野においては、プロダクトデザインとしての美しさだけでなく、例えばUIのレスポンスの快適さ、音声対話の認識精度、AIの賢さやふるまいの自然さなど、ユーザー体験(UX)全体のデザインが今後ますます重要性を増してくると思われる。
今回、2つの審査基準を踏まえて評価を行いながら、近年大きな変化のない商品ジャンルの商品群はこのままでよいのかといった点が議論になったり、逆にコンセプトは新規性があり面白いがプロトタイプの完成度がまだ低かったり、モックアップで体験ができず評価しようがないなど、審査に苦慮する場面もあった。
人々のライフスタイルや価値観が多様化し、技術進化のスピードもますます加速する時代において「革新性」と「完成度」を両立することはもちろん容易ではないが、今後それらが高いレベルで両立されたプロダクトやサービスが多く登場することを期待したい。
ユニット6は家具・住宅設備のカテゴリーで、今年もたくさんの応募があった。本年このユニットからは、4つのベスト100が選出された。
ユニットを超えて審査委員会で評価された、これらの製品がどのようなモノであるかを考えられたらと思う。
ダイキンのエアーコンディショナー「小空間マルチカセット ココタス」(17G060516)は、書斎や茶室、キッチンや洗面室、子供部屋などの日本の住宅や空間に多く存在する狭小空間の為に必要なサイズのエアコンである。
リンナイのガスビルトインコンロ「RHD312GM RHD322GM」(17G060565)は、ガス火の良さとIHの良さを上手く融合しており、頑丈な五徳で安心感がありながら清掃性も良いものであった。
また、寺田電機製作所 壁用コンセント「UCWシリーズ」(17G060601)は、空間に必須なアイテムであるがノイズになっていたコンセントを、使っていない時にワンプッシュで存在を消せるようにしたことでノイズの解消に成功した。
最後に、LIXILのカーポート「LIXIL カーポート SC」(17G060609)は、2本の柱とアルミ押出材で構成された薄い1つの屋根という極めて単純な構成を、構造と設備面をクリアしながら見事に実現しており、完成度の高さが評価された。
これらの根底に共通することはどれも、「なぜ今までに無かったのだろう!」と思わざるを得ない製品であり、これが「新しいスタンダードになったらいいな!」と思わせる物であった。
一見普通だが、一度全てゼロベースまで立ち戻り、設置される空間を意識し、機能を絞り込み、詳細のディテールまで一貫して真摯に追求したからこそできた製品であることが分かる。
このような開発プロセスを踏んだと思われる日常の製品が、ユニット内だけでなく、ユニットを超えた多くのベスト100候補の中から選出されたことに希望を感じる。
「スマートパーキングPeasy」(17G070714)の自律センサーによる駐車シェアのネットワーキングや、「アマゾンダッシュボタン」(17G070712)の家庭の買物ニーズをワンボタンで直接配送に結びつける提案は、IoTによって都市の形を変えていく動きにつながるだろう。300kgの車体軽量化に加え,高水準の客室性能と安全技術を誇るフロントデザインが印象的な「日野プロフィア」(17G070700)、「シトロエンC3」(17G070643)は、エアバンパーをモチーフにトータルデザインしたスタイリッシュなC3を提案している。「テスラ Model X」(17G070644)は、高性能計算機を実装したインターネットネイティヴなモビリティデザインを提案、パナソニックの「ワイドディスプレイミラーレスモニターシステム」(17G070650)は、車をミラーレスにするだけでなく運転感覚を変える可能性がある。JR西日本の「トワイライトエクスプレス瑞風」(17G070630)は、オープンデッキによる鉄道の懐かしい移動体験の演出と内部デッキの工夫が光った。大胆な発想の追求と底堅いつくりこみによる社会問題の解決に向けたモビリティデザインの息吹が感じられた。YAMAHAの「TMAX530」(17G070671)は、高級感ある樹脂素材の拘りと、ハイアップされた排気とシートで独自の世界観を表現。欧州スポーツコミューターの新カテゴリーを確立したデザインが卓越の域に達していた。トヨタの「C-HR」(17G070639)は、ダイヤモンドをモチーフに車体を斜めにカットし、上部をクーペのようにデザインしている。安全技術装備のつくりこみ精度も高く、最高水準の車両デザインと評価された。「TRAIN SUITE 四季島」(17G070629)は、震災に列島が揺れた2011年に開発をスタート。東北の美しい川面の風景が見えるように下向きに設けられた小さな窓、南部鉄器のダブルアーチによる広い客室、地域管理区の運転士による誇りをもったオペレーションが、非電化区間用に実装されたバッハのエンジンなど高い技術に支えられている。震災から立ち上がろうとしている東北文化を再編集するためのフラッグシップデザインとして高く評価した。
「移動」に関わるデザイナーは、安全や環境の制約下で、変わらぬ価値の体現とその変革に形を与えることが同時に求められる。質の高いデザインと、イノベイティブな提案が交錯した一年だった。

-
アートディレクター/デザイナー
- ユニット08:医療・生産プロダクト
B1-01 業務用装身具、B1-02 事務用品・工具、B1-03 農具・農業用機器、B1-04 生産・製造用機器・設備、B1-05 素材・部材/生産・開発・製造技術/製造法、B1-07 研究開発・実験用機器・設備、B1-08 医療用の機器・設備
ユニット8は、正確性や安全性が強く求められる医療機器や産業機器といった分野を対象にしているカテゴリだ。共通している事は、外観において華美な装飾は不要、堅実かつ誠実であること。長年にわたって着実にノウハウを蓄積し、確実な歩みを続けた結果として評価される「信頼」こそが価値と認められる分野だ。これこそデザインの本質でもあり、まさにそれを求められる。
本年は、従来の流れを踏襲しながら深化を遂げた文脈と、これまでの概念を覆す飛躍的進化の文脈、という二極化が顕著であった。前者が、信頼を裏切らずに、さらなる美しさを追求した製品であるのに対し、後者は、100年に一度あるか無いかというスケールで、通例を覆すイノベーティブなデザインを実現している。
昨今はIoTやウェラブルのトレンドによって、センサー、バッテリーの小型化の進歩がめざましい。そのような背景もあいまって、長年抱いてきた思想や研究成果を、このタイミングでリリースすることができた極小医療製品などは、まさに本年度の代表格といえよう。
本分野のデザインにおいて総じて言えることは、部品変更による機能性の向上などではなく、俯瞰的視点と柔軟な発想をもって、「社会システムとして成立するか?」にチャレンジする次元に突入してきている、ということだ。例えば技術革新によって可能になった特徴的機構の実現と、それによるコスト削減や環境への配慮も提案に織り込まれているものも多い。もはや解釈を捉え直す分岐点に来ているのだ。このことから「個」の主張というより、社会の仕組みとして個がどのように生かされるべきか、という観点でデザインされる時代だと分かる。
本カテゴリは一見地味に見えがちな分野であるが、若いベンチャー企業の応募があったことも注目すべき点だ。変化する社会基盤形成への貢献性が高く、進化と深化の可能性を多分に含む分野であることから、新たな視点でデザインを再構成する対象として、大変意義深いことは間違いない。

-
インテリアデザイナー
- ユニット09:店舗・公共プロダクト
A1-15 店舗・販売用什器、A1-16 公共施設用機器・設備/公共用家具、B1-06 業務用厨房機器、B1-15 業務用店舗什器/商取引用業務機器、B1-16 業務用公共機器・設備、B1-17 オフィス家具/業務用照明器具、B1-18 業務空間用の設備
本ユニットでは、商業・公共施設の領域で使用される文房具から家具、機器・設備・建材など、多岐にわたる製品が対象となる。本年度は時代に即した価値観を提供する製品、課題解決への取り組みがあった。
「学ぶ」「働く」に関わる文房具類は、PCなどのデジタル機器をほぼ誰もが使用している現況において、新しい視点や新たな「紙の価値」を提供しているものを評価した。変わらず要求されている従来製品についても、デザイン性・機能性を判断・評価している。働き方・学び方の改革が続くなか、椅子やテーブルなど身体と関わる家具は、多様性のあるもの、想定される使用シーンに焦点を当てたものなど、ユーザーを捉えた選択肢が豊富にあり、中間クラスの価格帯の製品においても高いクオリティーであった。空間を構成する間仕切りは、可動タイプや造作工事のいらない設置システム、既存間仕切を活用した減災建材など充実度が高かった。
人材不足・人件費削減の観点から、セルフ型レジの開発が活発であったが、かたち・使い勝手において評価が集まらず、残念な結果であった。スポーツ・ヘルスケア製品にも状況を捉えたデザインが求められた。公共施設のプロダクトや家具、建材においては、機能としての堅牢さとメンテナンス性に着目し、評価した。意匠性とともにメンテナンスに着目し性能を上げた内装材は、使用範囲と活用の場が広がることが期待される。
コンパクトな製紙工場をオフィス内に設けることで、情報保護とエネルギー・コスト削減を先進技術によって合理化した機器は、見せる・見られるオフィス空間のデザイン性も考慮していた。環境と人に調和する次のスタンダードを創造する姿勢を評価した。
土木関連では、従来製品に防草工法を採り入れ、費用軽減に効果をもたらす製品や、マンホールの突起形状による利点の開発など、関係者もスムーズに理解できる、現行品のアップデートによるソリューションが見られた。
国産材によるものづくりを商業・公共施設で提案することは、国内資源の活用、CO2排出削減など、環境の問題への関心を都市から地方まで提示することを可能にした。また木質素材を使用することで、居心地の良い空間を実現し、提供する側・使う側の環境問題への意識向上にも繋がる。内部のみ木質素材を取り入れた洗練されたサッシも現れている。
社会の中で使用されるモノのデザインには、環境や他者に対する配慮と調和、安全性に無関心ではいられない。社会貢献を考える姿勢が製品に表れてきている。

-
建築家
- ユニット10:住宅(戸建住宅、共同住宅、小規模集合住宅、工法・構法)
A2-02-01 商品住宅/工業化住宅、A2-02-02 個人住宅/インテリア、A2-02-03 集合住宅、 A2-02-04 その他住宅・住空間、A2-05 住宅用工法
今まで住空間ということで一つの審査ユニットだった住宅と集合住宅が、今年から二つのユニットに分けられることになった。私は住宅や小規模の集合住宅の方の審査に関わらせて頂いた。ハウスメーカーの住宅、工務店の設計施工の住宅、設計事務所が設計した住宅デヴェロッパーの企画したもの、それらを構成する部品など、色んな分野からの応募があった。それぞれに成立背景が違うものを一様に審査するのは難しい。それぞれの分野の中で、応募された作品が人の暮らしや社会をより良くするためのデザインとして一歩抜きん出ているものなのかどうかを考えながら審査した。
ベスト100に残ったのは、「竜美丘コートビレジ」(17G100952)、「KUGENUMA TORICOT」(17G100978)という2つの賃貸住宅、そして「無印良品の小屋」(17G100950)、「トレーラーハウス[住箱]」(17G100951)という小さな小屋だ。賃貸住宅の方はどちらも、ただ単に住宅として機能するだけでなく、コミュニティーを作る仕組み作りにまで発展出来ているところを評価した。特に竜美丘コートビレジは、郊外の賃貸住宅における駐車場のあり方を変えるところから始まって、1階のそこここに人がたまりたくなるような場を実現させている。実際に週末のマルシェなども活発に行われ、プロジェクトとして成功しているようである。建築という物を通して、地域の人と人が出会い、絆を育むという事づくりが成功している点が素晴らしい。集合住宅のあり方を一歩前進させている作品として評価した。
無印良品の小屋は最小限の寝るだけのスペースの小屋である。豊かな自然の中に置く事で、別荘とテントの中間的な存在として機能する事が目論まれている。トレーラーハウス「住箱」は持ち運ぶことも想定した小屋である。どちらも気軽なセカンドハウスを持つという新たな価値観を世の中に提示出来ているところを評価した。「山根木材のちいさな家」(17G100977)は、実際に暮らすことが出来る最小限の小屋であった。ミニマルな住空間が複数受賞したところに時代性を感じる。
A2-02-01 商品住宅/工業化住宅、A2-02-02 個人住宅/インテリア、A2-02-03 集合住宅、 A2-02-04 その他住宅・住空間、A2-05 住宅用工法
住宅の中でも、大規模な集合住宅や面的開発の戸建住宅が中心のユニット11の作品は、その特性からいって、単体のデザインや性能への評価に加えて、それが周辺環境に対して大きな影響力をもち、その影響力が長時間にわたるという観点からも評価されるべきものであろう。選出された作品を振り返ってみると、そうした周辺環境への配慮、時間を取り込んだスタンスが建築のデザインの中に息づいているものが多かったように思う。言い換えれば、建築単体の「もの」としてのデザインのクオリティとプログラムや取り組みの実態といった「こと」が、ともにそろった作品が結果的に選出されるに至った、といえるだろう。
今年のユニット11の応募作品を概観すると、そのファサードなどの外観のデザインに傾注したもの、まちづくりなどソフト面を計画に取り込んだもの、それに加えて、間取りの可変性や改修の可能性を広げるような作品に大別される。大規模な集合住宅でも住戸の間取りへの提案が多くなったのは、居住単位の多様化やライフスタイルの多様化に対応したものとして注目に値する。しかし、既成の住戸プランの連続が大半を占めているのも現実である。単身居住者の増加、しかも高齢の単身居住者の増加などを考慮すれば、プログラムと連動したさらなる提案が望まれるし、集合住宅というジャンルはそれに答えうる可能性をもっていると思う。高齢者施設、一般のマンション、戸建て住宅、といったビルディングタイプにとらわれない発想から新たなデザインが創出されることを期待したい。
また、環境に対する取り組みは単に技術的なアプローチにとどまらず、生活のスタイル、コミュニティとともに環境共生が組み込まれた作品がでてきた。これは、環境共生が広義なものとして展開している証左として、多いに評価できるし、成熟した日本社会のデザインとして発信できるジャンルと言えよう。

-
建築評論家
- ユニット12:産業公共建築・建設工法
A2-01 店舗内装設計・インテリア・公共空間、A2-03 公共用の建築・施設、A2-04 街区・地域開発、B2-01 業務用空間・内装、B2-03 業務用の建築・施設、B2-04 土木構造物、B2-05 産業・公共用建築工法
ユニット12では、インテリアから建築、そして土木までの広範な領域を扱う。したがって、ダムや橋梁も入るため、おそらくグッドデザイン賞でも最大規模の作品も含まれる。もっとも、インテリアや土木の応募数はそれほど多いわけではなく(今後もっと増えてよいだろう)、全体の内訳は建築作品が中心となる。近年、使い方やソフト面での興味深い試みも増えているが、それは他のユニットで審査の対象になりうるため、基本的にはモノとしての建築そのもののデザインがすぐれているかどうかを重視した。その際、ただなんとなく空間の雰囲気が良いだけでは、グッドデザイン賞では物足りないと考え、エッジのある特徴を持ちながらも、それを全体的なデザインに融合したものを評価している。
以下、ベスト100となった受賞作を中心にポイントを述べておく。例えば、「太田市美術館・図書館」(17G121062) や「Good Job ! Center KASHIBA」(17G121090) は、既存の方法論の洗練ではなく、これまでにない空間の形式を創造しており、発明的なデザインである。「三角港キャノピー」(17G121048) は、プロダクトとしての完成度が高く、構造と素材から導く美しい造形と周辺環境とのマッチが高く評価された。「福山市本通・船町商店街のアーケード改修プロジェクト」(17G121055)、「天理駅前広場コフフン」(17G121053)、「OM TERRACE」(17G121054)や「まちなか交流広場 ステージえんがわ」(17G121068) などは、現在の地方都市が共有する問題にとりくむ。コフフンは意表をつくシンプルなデザインによって都市のイメージを変えるほどのアクティビティを刺激し、アーケード改修は地元の建築家ならではの、手厚い関わりで実現したプロジェクトだが、同じ問題を抱えた他の地域でも参考になる事例だろう。「also Soup Stock Tokyo」(17G121111)は、単体で閉じることなく、地域に貢献する試みをデザインによって増幅した。「陸前高田市立高田東中学校」(17G121079)や「山元町立山下第二小学校」(17G121081)は、東日本大震災の後、ついに仮設住宅ではなく、復興建築としてデザインの力を発揮することができた重要な作品である。また素材という観点では、「小松精練ファブリック・ラボラトリー」(17G121132)や、「大光電機株式会社技術研究所」(17G121129)は、自社製品を用いた施設だが、いずれも新しい建築の要素を魅力的に組み込んでいた。
受賞作を振り返ると、特殊解のように見えながらも、さまざまに展開しうる汎用性をもち、より良い未来を切り開く空間のデザインが、より高い評価を獲得したと言えるだろう。

-
クリエイティブ/テクニカルディレクター
- ユニット13:メディア・パッケージ
A3-01 宣伝・広告・メディア・コンテンツ、A3-02 食品、パッケージ、B3-01 業務用メディア・コンテンツ/ブランディング・CI、B3-02 業務用のパッケージ
今の時代の「時代を写す鏡」は何なのか?3年間グッドデザイン賞の審査に携わった私としては、また、ものづくりに携わる一人の人間として、審査はまさに時代を読み取るものであり、受賞対象を世に出す責任を感じながら、今年も慎重に審査員の方々と一つ一つ応募作品を見させていただいた。「ものは大量消費されるものであるべきか?」「今までの伝統を守るべきか?」など様々な議論が起こる中、今年の作品を審査したが、今年の傾向として「愛着を持ってものを道具として使う」という観点が非常に強く見えたと思う。特に我々のユニットでは、パッケージでは環境に優しく、長く使える、今の時代にあるべきデザインが色濃く出たのと、コンテンツに関しては、単純にコンテンツの中身だけではなく、そのコンテンツが展開される場所や作り上げられる経緯等今まであまり前に出てこなかった因子が強く、すべてのバランスが良い作品が数多くエントリーされていた。今の時代は、比較的テクノロジーがふんだんに使われたものに注目が行きがちであるが、信念や哲学、ものに対する思いも含めた取り組みも数多く読み取ることができたと思う。
個人的に印象に残っているのは「INDUSTRIAL JP」(17G131197)。町工場が今までのイメージとは全く違うトーンで描かれる映像で、中小企業が多い日本のものづくり産業を、これまでとは違う切り口でPRすることが出来るコンテンツとして非常に良くできた仕組みだと思った。もう一つは、「さんち 〜工芸と探訪〜」(17G131191)。地道に足を使って見出した工芸品を最終的には自社ECサイトで販売をする事で、工芸の火を絶やさないようにする中川政七商店の試みだ。これは本来当たり前のことだが、今の時代の人々から見えている視野の狭さを指摘された試みであった。
コンテンツもパッケージも道具であり、それがどこからどのようにやってきて、私達をどこに連れて行ってくれるのか。突出したデザインやテクノロジーだけではなく、本当の意味でのモノのあり方がもう一度見直されるべき時代に入ったと感じた。

-
インタラクションデザイン研究者
- ユニット14:一般・公共向けソフト・システム・サービス
A4-01 ソフトウェア・サービス・システム/インターフェイス、A4-02 ソーシャルプラットフォーム
ユニット14は、一般や公共向けのソフト・システム・サービスを扱う分野であり、「コトのデザイン」とも言える新しいデザイン分野である。今年はこの分野から7件ものベスト100が選出された。年々関心が高まり、デザインの質の向上が見られる分野である。
しかし応募作品は多種多様で新しい分野のサービスも多く、評価は大変困難であった。議論の末に評価の視点は、現代社会に関する深い洞察、人の暮らしの重視、社会的意義、未来を切り開く可能性、細部の作り込みなどに集約された。
「日経ビジュアルデータ」(17G141208)は、膨大なデータを理解するデータジャーナリズムの分野で視覚化技術を応用した新時代のサービスである。「みえる電話」(17G141217)や、「しゃべり描きUI」(17G141219)は、聴覚障がいや言葉の壁などのコミュニケーションのバリアを解消するサービスであり、ユニバーサルデザインやインクルーシブデザインの成果と言ってもよいのではないか。「プリモトイズ キュベット プレイセット」(17G141242)や「ボーカロイド教育版と関連教材を用いた新しい『創作/歌づくり』」(17G141241)は、プログラミングの素養や音楽教育を支援するシステムであり、教育現場への深い洞察がデザインの背景にある。「さがデザイン」(17G141251)は、行政組織の革新であり、政策立案にデザイナーを巻き込むために新たに県庁内に設けられた仕組みである。更なる発展を期待したい。「日本経済新聞電子版アプリ/紙面ビューアー」(17G141207)は、デジタルに特化したニュースの提示法と紙の新聞の提示法を両立した新聞体験で、利用者視点や操作性が評価された。
この他にも多数の優れた作品が選出された。これからもこの領域への多数の応募を期待したい。サービスの評価は難しいが、異分野の人が見ても利用価値が伝わる審査情報の登録を望みたい。

-
デザインディレクター
- ユニット15:BtoBソフトウェア・システム・サービス・取り組み
B4-01 業務用ソフトウェア・サービス・システム/業務用機器インターフェイス、B4-02 社会基盤システム/インフラストラクチャー、B4-03 ビジネスモデル、B5-01 研究・開発手法、B5-02 産業向けの意識改善/マネジメント方法、B5-03 産業向けの社会貢献
20世紀型システムから個別最適化へ。ビジネス環境は大きく変化し、従来の仕組みに乗っているだけでは期待したビジネスの結果は得られない。商品や作業フロー、情報やサービスが本来あるべき関係で流れるよう、案件にとって最適化した仕組みを開発することで、突出した成果を生み出す時代だ。特に課題が浮き彫りとなっている業界では、根本的な解決に向けた新しい試みが次々と実行されている。
ユニット15の応募数は、昨年度に比べて大幅に増加した。これは実質的な取り組みの裾野が広がったことによるものだろう。今年とりわけ目覚ましい提案があった分野は、農業と医療関連だ。どちらも大改革が期待される分野だが、これまでデザイン的アプローチが介入しにくかった。ユニット15における上位受賞の優れた事案では、それぞれの業界が持つ本質的問題に取り組んだ解決が、鮮やかなアイデアによって事業化されている。
仕組みのデザインプロセスは、人や社会に与える価値の創出を目標にして、解決すべき問題の本質は何かを、丁寧に見出すことから始まり、抽出した複数の問題要素の弱みを補完する構造的なアイデアを設計する。つまり問題要素同士を結びつけてWin-Winの関係を生み出すには、核となる戦略のアイデアが必要だ。さらに、Win-Winの関係が淀むことなく継続的に循環するための運用案や伝達表現を詳細設計する。そこに参加する人々の心の充足が達成できれば、解決を生む仕組みとして成立するのであり、クリエイティブなデザインが施されたことになる。
その際1つの鍵となるのは、適正な技術の採用だ。技術が弱みを強みに変える触媒となるのだ。優れた事業開発では、技術を巧みに用いてビジネスを裏打ちしている。その反対に人が行っていたことを技術に置き換えるだけの取り組みは、デザイン的アプローチとはいえない。アイデアによって生まれる価値を活かす思考と工夫が、デザイン的アプローチである。ビジネスがデザインされることによって、社会と個人の生活を変える活力が生まれる。この分野のデザインへの期待は今後も益々高まるだろう。

-
クリエイティブディレクター
- ユニット16:一般・公共向け取り組み
A5-01 教育・推進・支援手法、A5-02 個人・公共向けの意識改善、A5-03 地域・コミュニティづくり/社会貢献活動
ユニット16が主に対象とするのは、社会課題や環境課題を創造的に解決支援する「ソーシャルデザイン」の領域と言える。今年の応募を俯瞰すると、取り組む課題自体の多様化もさることながら、課題に対するアプローチの多様性も高まってきていると感じた。ひとつには、地域や世界が抱える社会課題が加速的に多様化し、深化してきていることがあげられる。地域が慢性的に抱える問題や国際協調が必要なグローバルな問題もあるが、日本が国際社会に遅れをとっている教育やジェンダーの問題、組織と個人の関係性の問題など、これまで眠っていた課題が表に噴出してきたとも言える。それらの課題に、クリエイティブなマインドで取り組むチャレンジも必然的に増えてきているのだ。
もう一つの理由は、対象とする社会課題の段階によってデザインが効くポイントが異なる点にある。審査委員会では社会課題を「人々の気づきを促し、意識を変える段階」「課題解決に向けた具体的な活動を促す段階」「課題が解決した状態を定着させるため、継続性のある仕組みをつくる段階」の3段階にわけ、それぞれの段階に対応した適切なデザインが考えられているかを議論した。気づきの段階であれば、認知を高めるだけでなく、課題に対する心理的障壁を効果的に払拭するコミュニケーションデザインになっている。活動の段階であれば、参加性が高くなる工夫があり、行動を促すモノやコトのデザインに新規性や話題性がある。仕組みづくりの段階であれば、ビジネスモデルや組織体制、活動スキームに実績や将来性がある、といった点で優れた取り組みが評価された。もちろんこれは審査の視点のひとつであり、応募者が思い描く「社会、世界、未来」に込められたビジョンやストーリー、取り組みの歴史、起点となった動機や社会への姿勢に感銘を受けた活動も多くあった。特に「個」の想いから始まったことが人々の良心に響き、全国に広がっていった活動もあって、その原点となった活動が応募されて賞を贈ることができたのは、審査委員みながグッドデザイン賞の意義を再確認することにもつながり、素直に喜びあえたことだった。
社会を良くしようというグッドプロジェクトはいくらでもあるが、それがグッドデザインと呼べるか、というと、そういうわけではない。グッドデザインとグッドプロジェクトの違いは、あえて一言で言えば、どれだけ他者とのつながりを深く想像しながら活動をしているかに尽きるのではないか。他者と自分たちとの関係を築こうとする想いや工夫のなかに、デザインという行為は自然に立ち上がってくるからだ。プロのデザイナーが関わっていなくても、「ここには優れたデザインがある」と感じるプロジェクトが共通してもっているのは他者への想像の深さなのだと思う。とりわけ「取り組みのデザイン」には目でみてわかる「カタチ」のデザインが明確に存在しないことが多く、審査側の想像力も問われる。あらためて、このことを深く考えさせられた審査だった。
韓国ユニットの応募対象は、例年通り技術進化と共にある情報機器関連と家電機器が多くを占めていた。その中でもディスプレイやスマートフォンなどの情報機器は、より薄く、より強固に、美しく、革新的なテクノロジーの進化を遂げていた。それらの機器には、上質な性能と体験が最高級品としての位置づけで体現され、他の追随を許さないそのパワーに一同圧倒された。車関連も去年と違わず、数多くのタイヤのエントリーがあった。欧州メーカーの高級車に採用されるなど、海外からも品質とそのデザイン性が高く評価されており、着実な進化を遂げていた。中小企業やベンチャーでは、生活や人の観察から生まれたアイデアを既存技術の応用やスマートフォンとの連携などで創意工夫に満ちた、すがすがしいデザインで表現されていた。規模のコンパクトさは、発案から商品化までのスピードの速さと、強い熱い思いを生みだしている。今後も更に活性化するであろうと思われる。生活家電では、空気と水への関心度の高さからか、それにまつわる多くのエントリーがあった。機能もデザインも研ぎ澄まされた商品が多く、高付加価値なモノから廉価版まで幅広い展開がなされていた。競争の激しさもあり、ユーザビリティーはもちろんのことインターフェースの細部の表現に至るまで、日本では見られない細やかな美しい表現も数多く存在した。ファニチャー分野では、高い機能性と価格感度の良い基本ラインの商品や、持ち運びしやすい、成長に合わせて変化できるなど、具体的な達成を明確に表現した良いデザインがあった。社会の変化を敏感に感じ取り、生活提案がなされた誠実なデザインが今後も増えていくと思われる。
最後に、今回はコトに関しての取り組みもいくつか挙がっていた。行政と地域住民との安全なまちづくりプロジェクト、廃棄される生地を用いたアップサイクルの商品開発など、地域住民や行政も巻き込んだストーリーのある今までにない取り組みが見えた。今後も更に様々な分野に広がりを見せることが期待できる。
台湾ユニットの審査を2年続けてさせて頂いた。全体を通した印象をひとまとめに語ることは難しいが、毎年新鮮な発見に満ち溢れ、記憶に残る作品も数多い。
一つにはOEM生産を行っていた企業が自社ブランドを立ち上げ、極めて質の高い製品を発表し続けていることが印象深い。台湾の真面目な国民性故のことだと思うが、特にパソコン分野は抜きん出ている。薄い、軽いといった性能はもはや当たり前で、その上でさらに日常的な使い勝手の中でのちょっとした気づきに支えられたきめ細かい配慮が年々向上している。こうしたユーザー目線の解像度を高めていくことは、食器や家電の分野においても見られた傾向だ。単なる機能性を超えた次元でのデザインの進化は、逆に僕たちの生活そのものに対する解像度も高めてくれる。
もう一つは、日本では見られないような新たな取り組みや、そもそもデザインと呼ぶ領域を拡張するような作品が多いことも特筆に値するだろう。例えば空き地を市民コミュニティの場として活用していくための取り組みと実践は、都市空間に於けるインフラや公共空間のあり方自体を問い直す社会性に溢れた提案だ。あるいは最先端の映像機器の広告を、単なるスペックではなく、むしろそれを利用する現場の状況をリアルに伝えるデザインと並走させ、見たこともない壮大な空間を出現させたり、会社の理念を多様なデザインツールを用いた一つの物語として提示するなど、新しいメディア誕生を感じさせてくれる作品もあった。
もう一点、廃れた技術をデザインの力を通じて継承していこうという商品も、ものができるプロセスとその喜びを伝えるものとして貴重だ。デザインの教育的側面を大切にするのも、やはり台湾らしさと言えるだろう。
こうしたデザインの価値は、日本の目線で評価していては見えてこないものが多いように思われる。むしろこちら側の評価の枠組みが問われているように感じられた。
中国・香港審査ユニットでは、中国全土および香港からの応募を対象に、有形無形を問わずグッドデザイン賞の全領域にわたって審査した。400点余りと限られた数ではあったが、デザインというフィルターを通して見ていくことで、中国の産業動向の一端をうかがうことができた。
近年の中国においては、サービス業の活性化と、製造業における自社ブランド製品の事業化が、産業競争力を高める原動力と言われている。サービス業では、電子決済の普及が後押しするシェアバイクやタクシー配車などの新しいビジネスが話題になっているが、今回の審査ではサービス業関連での強い提案は見られなかった。
一方製造業では、まず応募数の増加という数の面で、自社ブランド製品事業の動きを実感することができた。品質の面では、「機能と価格では満足できるが、デザインという、より包括的な視点で見ると、あと一歩及ばない」という近年の中国からの応募に対する総括的評価があるなかで、そうした既成概念を覆したXiaomi(小米科技)の製品群が目を引き、2件がベスト100に選出された。特徴は、表面的なスペックにとらわれることなく、ユーザーが必要とする基本機能を強化し、機種を絞って一点集中で造形と仕上げにこだわる、本来あるべきユーザー視点での開発を高いレベルで実現していることだ。Xiaomiは、スマートフォン事業で成功し、生活家電や電動バイクに事業を拡大しながら成長しているが、どの事業領域においても等しく高い水準で開発されていることからも、企業としてのデザインに対する意識の高さが感じられた。
先進国では、過剰生産で市場に商品が溢れているにもかかわらず、本当に欲しいものが見つからない由々しき状況がある。このようなユーザー不在の製品開発のあり方に対して、Xiaomiの開発姿勢は一石を投じるものであり、これからのものづくりの指針となるだろう。そして、世界市場に影響力を持つベンチャー企業が短期間に成長していることからも、中国の勢いを感じることができた。