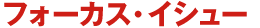フォーカス・イシュー・ディレクターが2017年度の審査を前に、イシュー(テーマ)に対して感じていること、デザインに対して期待していることを伺いました。

-
伊藤 香織
都市研究者/東京理科大学教授
共生とは幅広い解釈ができる概念です。いま社会的には、インクルーシブな社会に対する関心の高まりとともに、相対的に、さまざまな格差の拡大や、既存のコミュニティの分断化といった、人と人がともに生きていく存立基盤を危うくしかねない状況が進むことへの危機意識が強く働いています。そのため、共生すべき対象をある程度絞り込んで、その実現に向けたビジョンを描く傾向もみられますが、あたかも都市の広場における、あくまでも寛容な人と人との関わり合いのような、自然な認識と自然な理解とに支えられた共生のあり方が理想であるようにイメージしています。
多様な立場の者が共存できる空間・他者への想像力・そして自ら他者に関する知識を得ようとする明確な意志 — これらの存在を、共生社会の構築に必要な条件と理解して、いまデザインがその醸成にどのように作用しているかに着目していきたいと考えています。

-
ドミニク・チェン
情報学研究者/早稲田大学准教授
社会基盤というテーマを考えるために昨今の社会情勢を見ると、必ずしも進化しているとは言えません。進化を妨げている最大の要因は、「社会の分断」がさまざまなレイヤーで起こっていることではないでしょうか。楽観的にテクノロジーによって人類が進化できるという言説がリアリティを失ったいま、「進化」という概念を深めるためには、何が望ましい未来を妨げているのかについて社会全体を解剖してみる必要があるのではないでしょうか。分断に対しては「包摂」が重要となりますが、では包摂を促す社会基盤とは一体何か。たとえば情報と人との関わりとしての情報技術はひとつのポイントになります。その意味では、素材としての技術をどうデザインできるか考えていかなくてはなりません。私はデザインが、もともとの意図を超えたところにまで価値を届けようとする自律的な姿勢に可能性を感じます。ユーザーが自ら情報を判断して価値を表明する力を強められるようなデザインのあり方が、社会の基盤を成す力にもなりうることに期待します。

-
岩佐 十良
クリエイティブディレクター/自遊人 代表取締役
全国各地でローカリティを伸ばし、地域社会を活性化させる動きが盛んになっています。そうした活動はプロセスそれ自体が地域の活性を促すことは確かであっても、いかに質実の伴った成果を上げられるかが重要です。ただし、現状では経済的な効果が優先される傾向が強く、魅力的なデザインとしての成果にまで至っている事例はまだまだ少ないようです。
地域における活動では、同じ課題意識を持ち、もたらされる成果の意義・重要さに気が付いた者同士が担っていくことが大切であるように考えています。この点で、各地には優れた経営者や事業者は存在していても、地域の複雑な全体状況をふかんしながら魅力のあるアウトプットへ導けるという意味での「デザイナー」が少ないことも事実ですが、いまの時代は、それぞれの地域内で完結するマーケティング、地域の魅力を地域で独自に作り上げていくことが可能であり、そのための人材の育成という側面にも注目したいと考えています。

-
青山 和浩
システム工学研究者(工学博士)/東京大学教授
安心は安全と比較されて論じられる場合が多いですが、安全は設備やシステムなどの整備を通じて外的にもたらされます。これに対して安心は、人が自ら能動的に設備やシステムを理解し、腑に落としていくべきものです。また「いまこの瞬間の安心感」や「将来にわたる安心」など、安心を求める際の時間軸の存在も特徴的です。私たちが主体的に安心を築いていくためには、ものごとをシステムとして認識することを前提に、時間軸を意識し、不確実な未来を見通しながら、その全体像をつねに把握できることが重要に思われます。これまでの日本社会では,このような思考の重要性はあまり議論されることはありませんでしたが、近年ではシステム思考の意義が認識され、その思考を実践するための方法論やサービスなどもデザインされる事例が多くみられるようになりました。このような新たな潮流の中で、一人ひとりが自らの視点で安心を獲得できるようになることが、私たちが構成する社会の安心を創り出す上でますます重要になっていくものと考えています。

-
藤崎 圭一郎
デザイン評論家、編集者/東京藝術大学教授
学びとは、個人が社会に主体的に関わっていく態度そのものです。外部から知識やルールをただ与えられるということでなく、私たちが社会と関わる術を能動的に身につけていくプロセスにほかなりませんが、生涯にわたってそれを実現していくうえでは大きな課題があると考えています。まず幼児期〜小児期における個人の主体性を伸ばす教育が大事です。その一方で、日本では主体的存在としての個人を尊重するということが、他者との同調を強いることに転化される傾向があります。そうした過剰な同調の圧力を受けたかたちでの学びは、イノベーションやクリエーションの源となる、個人が「飛躍すること」を妨げてしまうのです。一人ひとりが主体的に「飛躍できる」社会であるよう、たとえごく僅かな幅の飛躍であったとしても見抜くことができ、許容できるセンスをお互いに高めていく、それが私たちにとって学ぶということの大きな意義であるように思います。

-
林 千晶
プロジェクトマネージャー/ロフトワーク 代表取締役
「働く」ということを、哲学者のハンナ・アーレントは「仕事」「労働」「活動」の3つに分解しました。いま、戦後のようなペースで社会が成長していくという呪縛から私たちは解放されつつあります。それとともに、自分にとっての働き方を考えたいという人が増えています。そのときに「働く」ことは、「仕事をする」「労働をする」ことよりも、「活動する」ことと同義になりつつあります。活動、すなわち人が生きることが働くことであり、働き方とは個人の生き方である、このような生き方をしていきたいという意志の表れが、働くということのイメージを形づくるようになるのです。
では、そのように何らかの活動をしたいと志す者同士が集まることで、一体何ができるのでしょうか?「働き方の改革」として、いま社会の高い関心が向けられているのは、まさしくこのような問いかけであるように感じています。たとえば働く環境としての企業も、活動をする者の集合体としてそれが何を成しうるのかを考えてみると、その可能性が見えてくるかもしれません。

-
吉田 龍太郎
プロデューサー/プレステージジャパン 代表取締役
日本ではもの作りの風土の上にさまざまな生活の価値が生まれています。ものを作り、使うことを土台にした暮らしの文化があって、暮らしという日々の経験を通じて見出される価値が大切にされています。そのためデザインについても、実際の暮らしの中で生かされることで体感されるよさというものがあるように思います。近年ではデザイナーの姿勢にも大きな変化がありました。デザイナー自身に消費者(ユーザー)としての目線が備わるようになり、自らの目と手を通じて得たことを伝えるよう努めています。Made in Japanブームに乗じるようなこととは違う、日本の生活価値の発見と発信を担う可能性を持ったデザインといえるでしょう。
そして、私たちが尊ぶべき生活の価値として、特に「継承」という概念が大事であって、決してそれまであったこととまったく別のものであるということではなくても、それでいてなお新しさが感じられるということに意義があるように感じています。

-
内田 まほろ
キュレーター/日本科学未来館 課長
人間は技術を生みだし用いる生き物です。技術を使うから人間だという言い方もできると思います。技術は私たちの生活において、必ず必要ですが、人と技術のインターフェースにあたるデザインとの関係性が明白かといえばそうではありません。実際、人間の生死や、何百年にもわたる常識を覆すようなイノベーティブな最先端の技術には、未だデザインが関わる度合いが少ないでしょう。また、次々と生み出されるそれぞれの技術に対して、社会のシステムの整備が追いついていないことも、明らかな課題といえます。
「先端技術の応用」という視点は、技術の進化におけるデザインの介在であると理解します。いかなる技術も日々進化している点では、つねに先端です。このイシューを通じて、技術が「人によって用いられるものである」という前提に立ち、デザインが、人と技術の間にいかに有意義なバトンを渡す提案がされているかを読み解くことができればよいと期待しています。
→ 2017年度のフォーカス・イシューと提言
→ 2016年度のフォーカス・イシューと提言
→ 2015年度のフォーカス・イシューと提言